米の価格が例年の倍近くに急騰し、私たちの食卓に大きな影響を及ぼしています。
かつては安価で手軽に手に入ったお米が、なぜこれほどまでに高騰しているのでしょうか?
その背後には、異常気象や政府の政策などが取りざたされているが、実は米の生産量は前年より18万トン多いのです。
本記事では、米の価格高騰の理由を分かりやすく解説し、その影響と今後の展望について考えてみたいと思います。
前年より18万トン生産量は増えているのに米の価格が高騰する真の5つの理由
理由1. 農家がJAなどの集荷団体に卸さず、高値で直接販売、備蓄している
一部の農家は、JAなどの集荷団体に米を卸さず、直接販売や備蓄を行っています。
昨シーズでの価格上昇により、一部の業者や外国人が農家から集荷業者より高値で買占めし、さらなる価格上昇を待って転売を狙っているということです。
この動きは、農家がより高い収益を得られる一方、結果として市場に供給される米の量が減少し、価格が上昇しています。
また、縁故米と言って、農家から親戚縁者に安値で回しているとも言われています。
理由2. 南海トラフ巨大地震の備えにより、各家庭で米を備蓄しようと買い溜めした
南海トラフ巨大地震の発生が予測されており、これに備えて多くの家庭が米を買い溜めしています。災害時には、長期間保存できる食料が重要となるため、米の備蓄が進んでいます。
しかし、この大量の買い溜めが市場に供給される米の量を減少させ、価格上昇の一因となっています。
また、マスコミの報道で「令和の米騒動」というキャッチフレーズや、一部のスーパーの棚から米が品切れするシーンを放映することで、不安をあおり拍車がかかっていると言えます。
理由3. 転作奨励金を農家に与え、実質的な減反政策が続いている
政府は、農家に対して転作奨励金を与えることで、米以外の作物への転作を促進しています。これにより、米の生産量が減少し、価格が上昇しています。
転作奨励金は、米の過剰生産を防ぐために導入されましたが、現在では米の供給不足を引き起こす要因となっています。
農家が転作を選ぶ理由は、他の作物の方が収益性が高い場合や、気候変動によるリスクを分散させるためです。これにより、米の生産量が減少し、価格が上昇しているのです。
理由4. 作況指数にカウントされない安価米(ふるい下米)の不足
近年、作況指数にはカウントされない安価な米、通称「ふるい下米」が不足しています。この米は主に加工用や飼料用として利用されており、通常の食用米とは異なります。
安価なため、多くの消費者や業者に重宝されていましたが、最近の不足により、通常米が転用され価格が上昇しています。
この不足の原因は、米の生産量が減少していることや、農家が高付加価値の品種を優先して栽培するようになったことです。稲の成長期に雨が少ない場合に影響します。
理由5. 単一ブランド、生産地を統一して売る傾向があり、量が揃いにくい
最近では、単一ブランドや生産地を統一して販売する傾向が強まっています。これにより、高品質な米が提供される一方で、供給量が限られてしまう問題も発生しています。
特定のブランドや地域の米に人気が集中すると、需要に対して供給が追いつかなくなり、価格が上昇します。さらに、気候変動や自然災害が特定の地域に影響を与えた場合、その地域の米の供給が大幅に減少することが懸念されます。
米の高騰はいつまで続くのか?
米の価格が高騰している背景には、さまざまな要因が複合的に絡んでいます。
政府が3月半ばを目途に業者に21万トンの備蓄米を放出すると発表しました。
また、買占めした米を倉庫で保管できるのは、冷蔵・防虫がいらない寒い時期のみで、暖かくなってくると市場に出始める可能性があり、4月には価格が下落していく公算が高いです。
以前のマスク不足の後に転売ヤーが一斉に居なくなった時ように供給が正常化されると価格が元に戻ると推測されます。
一部の情報に惑わされ、買い溜めをしたりしない。高い水準価格の米は買い控え、冷静に価格が元に戻るのを待つことが求められているように思います。
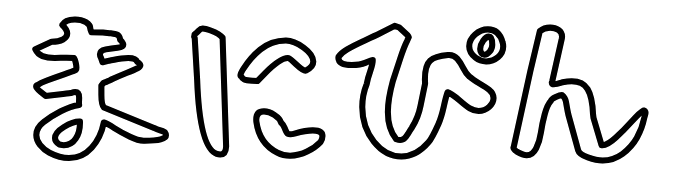



コメント